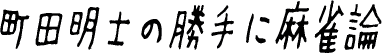
![]() 20〜31を追加(2004/1/16)
20〜31を追加(2004/1/16)
1.うまい人へたな人 2.麻雀をやらない人 3.早い段階で字牌の処理することについて 4.字牌の危険性について
5.止めた? 6.東場を乗り切る 7.七対子をあがる 8.1x1x1x1?1x3? 9.あがれなければ
10.鳴かれて変わる流れ 11.何場? 12.河を見よう 13.予感 14.なぜあと1順まてないのか
15.どのぐらいの確立で振り込む? 16.振り込む時の反応 17.得意役 18.ベタオリ 19.安全牌ばかり切らないこと
20.最低限のマナー 21.絞らないことは利点?失点? 22.絞ることについて 23.鬼ごっこ
24.2択がもたらす微妙なズレ 25.事故だよ事故 26.引き際と攻め際 27.予感 28.決め打ち
29.七対子の作り方 30.手ナリじゃあがれない 31.1鳴き2鳴きの謎
戻る
| 1.うまい人へたな人 | △ |
麻雀が下手な人は字牌の使い方と、鳴きの仕方が下手な人だと思う。 そりゃ当たり前なんだけどね・・・。 鳴かない麻雀だったらはっきりいってツモって捨てるだけなんだからさ・・・。 それだけで麻雀してたら麻雀は運のみになってしまう。 鳴きも考慮した麻雀ができないようなやつはやっぱりどんなに運がよくったって下手。 後は当たり牌を絞れる人と絞れない人だろうが これは難しいね 俺も絞れないし |
|
| 2.麻雀をやらない人のなぞ | △ |
俺ははっきり言ってこんなに奥が深いゲームはないと思ってる。 麻雀をしてない人は人生を損してると言っても過言ではない。 んで、大体麻雀をやらない人にもいろいろと理由があるんだけど、 中でも役が覚えられないとか、点数が数えられないとか? そんな難しくないぞ?っていうか簡単に覚えられるぞ? |
|
| 3.早い段階で字牌の処理することについて | △ |
3枚集めないと役に立たないと思われがちだが、 実際にはそんなことはない2枚あれば鳴くこともできるし、 2枚持ってれば安全牌になる可能性も高い、 だから1枚持っていたってもう1枚持ってくれば 使えるものになる 字牌とは3枚集めるものではない ということがわかってない人が多い さらに自分の配牌が悪いとき 1番に字牌を処理する人はおかしい こんな手の時こそ字牌を2枚にして鳴いてあがるのが 最良と言える 早い段階で重なっている字牌を2枚切り落とし タンヤオ・ピンフへ向かおうとする人は信じられない もちろん手役をあげるために切ることは全然ありである さらに字牌を自分の中に止めておくと 相手の手を遅らせることにもつながる これは自分の手が遅れるとは考えない 不要牌なんて配牌時にですら大抵3〜4枚はあるのだから そのうちの何枚かを字牌にしても 全く自分の手は遅れてないのだ 相手が重なる前に切っておけばよかったとは考えない これはケースバイケースだし 自分にとっていい事の方が絶対的に多い |
|
| 4.字牌の危険性について | △ |
前章で字牌の安全牌になる可能性について話をしたが 2枚残した字牌は本当に安全なのだろうか? 前章で言ったように相手が重なってから切って 鳴かれたりあがられたりすることがないだろうか? 2枚ある字牌も河に1枚以上捨てられていなければ 決して安全であるとは言えない さらに1枚残した字牌が全く重ならなかったとき この字牌は逆に危険牌になる それならば「抱え死ね」という前章後半の話につながる 自分があがれないなら相手もあがれない という考え方も悪くはない(常に良いはずはない) 特に自分の手が酷い時は尚更だ これは上述にもあるよう 自分の手が悪い時に字牌を真っ先に手放すことは 愚の骨頂だ この良し悪しは終わってみなければわからないことが多いが 使い方がうまければ良いことの方が多い |
|
| 8.1x1x1x1?1x3? | △ |
麻雀とは4人でやるゲームなために 基本的には自分1人で残りの3人に勝つ というイメージでいいだろう しかし、ときには3人で1人の人を抑えなければ いけないときもある 明らかに鳴かれるのがわかっている牌は鳴かせない のってきているトップを早流しする などのケアをしていかないといけない それを自分のことだけ考えて 鳴かれそうな牌をぽんぽん捨てたり のっているトップにもケアをしないで 有効牌を鳴かせているようでは駄目である |
|
| 14.なぜあと1順まてないのか | △ |
字牌をとっておくが 周りから字牌の有効性が感じられなかったり 多数ある字牌の中から ひとつを選択して切るときなどよくあるが その次の順で捨てた字牌重なる ということは本当によくみる 一体何が悪いのか これはわからない |
|
| 15.どのぐらいの確立で振り込む? | △ |
これは3順目のリーチやダマテンのケースは除く 1.ピタリ当たり牌を読んで止める 2.当たり牌群で予想をたてて止める 3.当たり牌群で予想をたてたが振り込む 4.当たり牌はわからなかったけど振り込まない 5.当たり牌がわからなかったために振り込む 圧倒的に4が一番多いだろう 続いて2・3・・・ そして5・1となるだろう そう考えると 麻雀なんて思ったほど振り込まないものだと思う もしくわ振り込んでも仕方がないもの 当たり牌なんて8/136ぐらいのもの 当たり牌群で予想が立てられれば 十分である |
|
| 16.振り込む時の反応 | △ |
前章の話ででた振り込むケースの話だが 1はかなり嬉しい しかもそれを使い切って 逆転で上がりきったら最高だろう 2・3についてはある程度しょうがないだろう 当たっていたらいいし 切ることもそうはない でもテンパイが入ったときは勝負するだろう そこで振り込んでも何も後悔することはない あぁ やっぱりね程度の話だ 5についてもしょうがないところがあるのだが ただそれでも安全そうな牌を捨てるケースと もう関係ないと危険そうな牌を捨てるケースがある 後者はまだ諦めがつくが 前者の方で振り込むとちょっとへこむ 特にわからないけどかなり安全と 根拠のない自信を持って捨てて振り込む時は 悲しい |
|
| 18.ベタオリ | △ |
ベタオリすると次から配牌がこない まぁはっきり言ってオカルトの世界だな 実際そうだと思う反面 そうでもないかとも思ってる 麻雀のロジックの中に相当オカルト的な話も 含まれると思ってるので 別にこれはこれでいいのだが やっぱりリーチやテンパイ者に対して メンツの中抜きなんかしてまで 降りてしまうと 戦意喪失とみなされて(誰に?) 次から流れがなかなかこなくなると思う ベタオリできないと やっぱりメンツの中抜きとかは なかなかできないから 半分下りてるのに 危険度Bぐらいの牌を切ってみて 当たったりする これがなかなか失くしたいのに 失くせない罠だ ベタオリすると配牌こないという ロジックを崩すしかなさそうだ |
|
| 19.安全牌ばかり切らないこと | △ |
例えば振込みたくない一心で安全牌ばかり切ること これ自体は悪いことではないのだが 例えば自分が3万を3枚使っていた時に3万を壁にして 2万を切る かなり安全な行為だが(当たる可能性はある) しかしこれによって3万を3枚も使われているために 他の人が浮いていた2万が切ることができるようになる そして2万を切ることができた人が うまく乗り切ることができてベタオリする必要がなくなり 少し前進して何かを勝負し それが自分の助かる牌となる なんてうまくいくことは毎回毎回あるわけじゃないが 少し自分が進展することで 自分も進展することもある ベタオリばかり しないことにはこういう利点もある |
|
| 21.絞らないことは利点?失点? | △ |
他人に必要な牌が自分の手にあることを 失点だと思う人が多い 確かに麻雀というのは どれだけ早く聴牌するか というゲームだ しかし実はそれは言葉が足りてなく どれだけ相手を早く聴牌させないで 自分が早く聴牌するか というゲームなのだ だから牌を絞ることによって 自分の手役が遅くなることを 失点だと思う人が多いが 実は相手の手役を遅らせてることで 利点なのだ だから絞らないで他人の手役を進めて そして結果的に自分は降りてしまい 他人があがるということは まさに愚の骨頂 絞ることは利点なのだ |
|
| 24.2択がもたらす微妙なズレ | △ |
例えばの話 浮いてる2万と8ピンを どっちに先に切るか 本当にたまたまの話になってしまうが もし先に2万を切ってしまうと その時下家は3万しかもっておらず 鳴かれない 次に自分はいい牌を引い聴牌する しかし8ピンを先に切ると その後下家が4万をつもり 次に捨てる2万をチーして 流れが変わり ツモがずれてあがれない ここらへんは麻雀の どうしようもない領域なのだろうか・・・ |
|
| 25.事故だよ事故 | △ |
事故だよ事故 と言われるような 振り込みをしてしまった時 等に起こる「へこみ」 負けトランス状態 こんな時に 自分が再浮上するきっかけというのは 一体なんなのだろうか? そこから回復するのは非常に大変である はっきりいって簡単に一回あがるのも 至難の業となるだろう そんな状態からもとの状態へ回復するのは 時間と技術が必要となってくるだろう 麻雀というものは完璧に全てを こなすことは絶対にできないため 自分以外の誰かが ある時ある瞬間に犯すミス そのワンチャンスを生かし その局だけでもものにする 万年4位から3位へ脱出をするなどの 他人のミス+自分の成功が 合わさると その時 負けトランスから脱出することができる |
|
| 26.引き際と攻め際 | △ |
麻雀というのは 引き際と攻め際の やりとりが難しいものである 前章までに書いてあることを読むと 攻めた方がいいのか? 引いた方がいいのか? 両方の利点が書いてある そもそも行くときにいかないと 他の人を上がらせるだけであるし しかし一方通行で行ってしまうと 結局他人に振り込む という結果にもなってしまう 行くところを行き 引くところを引かないと 勝てないものである これがわかっていても どこにその境目があるか わからないもので のっているときは どれだけ行っても大丈夫だが のってないときは あっさり振り込んでしまうのだ この境目を見つけられたら 麻雀で負けることはないだろう |
|
| 29.七対子の作り方 | △ |
作りづらいと思われてるが 確かにどれが来るかなんてわからないが ある程度は考えて打てば少しは確立はあがる まずは河と手役で対子場を見つけよう これは最低限の条件 それとスジは対子にはやはりなりやすい 続いて河から他人が持っていなそうな牌を選択する これも熟練した人ならある程度絞ることができるだろうし これが一番必要 1枚も切れていない牌を取っておきたがる人がいるが そういう牌は使われている可能性も高い 逆に2枚切れの字牌はくる可能性は十分ある なぜなら確実に1枚山に残っているからだ 他の人に1枚行ってるのだから 残りのもう1枚は自分のところに 来てもおかしくないのである(これは確率論的に嘘かも) |
|
| 30.手ナリじゃあがれない | △ |
伸びないと感じる手配は どうすればよいのか? 捨て杯や他人の河をみても どうやってもあがれないと 感じる 場合 その時の局はどんな 進め方が正解だったのだろうか? 麻雀というのは 3人でやるものなので やはり他人の鳴きによる ツモの変化の影響は大きい 実際に鳴かれたときに ツモの流れ変わったというが それは果たして本当なのだろうか? 他人を鳴かす牌を捨てていれば あがれたのか? 無理やり自分が鳴いていれば あがれたのか? |
|
| 32. | △ |
| 33. | △ |
| 34. | △ |
| 35. | △ |